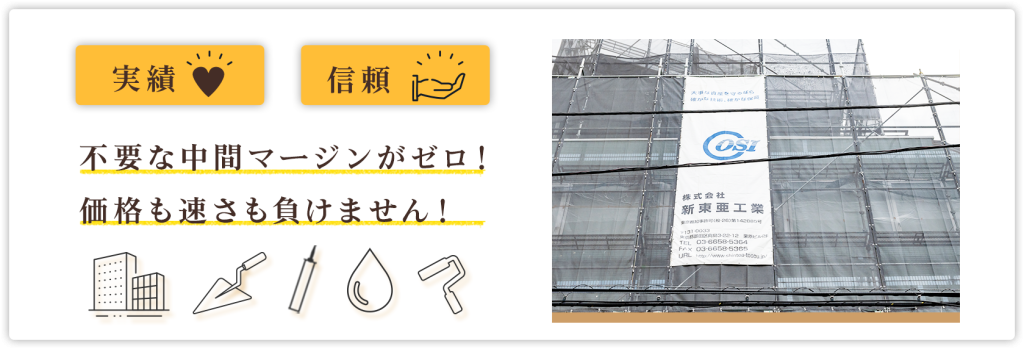家や住宅の防水工事はいつするべき?
マンションのベランダの防水工事は?
ベランダの防水工事の重要性や効果的な方法を解説。プロのアドバイスや選ぶべき素材など、ベランダの防水工事に役立つ情報をご紹介。
目次
ベランダの防水工事の重要性
ベランダは雨や湿気などさまざまな要因で劣化しやすい箇所です。
ここでは、ベランダの防水工事を実施する重要性を3つ解説します。
- 水漏れのリスクを軽減
- 建物の耐久性を向上させる
- 快適な居住環境の確保
水漏れのリスクを軽減
ベランダは、雨や湿気などにさらされることが多いので、適切な防水処理が必要です。
防水工事が適切に行われていないと、雨水や湿気がベランダの下へ侵入し、建築資材の木材や金属の腐食・錆びの原因になります。
またアパートやマンションの2階以上にお住まいの方や、一軒家にお住まいの方など、雨水が漏れて下の階が雨漏りする可能性も考えられるでしょう。
このような水漏れを起こすと住んでいる場所によっては家族以外の方々に多大な迷惑をかけることもあります。そのため、水漏れのリスクを引き起こしやすいベランダの適切な防水工事が重要です。
建物の耐久性を向上させる
ベランダの防水工事を実施することは水や湿気が建物内部に侵入することを防ぎ、建物の耐久性を向上させる効果が期待できます。
このとき、ベランダの排水設備や水切りなどの設置も重要です。適切に設置された排水設備は、雨水が溜まらず、建物内部に水が浸入することを防ぐ効果が期待できるでしょう。
快適な居住空間の確保
ベランダの防水工事を実施することは、快適な居住空間の確保にも繋がります。
例えば、ベランダの防水工事が適切に実施されていない状態が続くと、劣化が進行して外観が損なわれる可能性があります。これはその建物に住む住民にとって快適な居住空間とは言えません。
また、防水工事によって建物内部に雨水や湿気の侵入を防ぐことで、雨漏りなどの被害を未然に防げれば建物自体の寿命を延長させられるだけはなく、トラブルのない快適な居住空間を確保できます。
防水工事の種類と特徴
次は防水工事の種類は主に3種類です。
- シート防水
- 塗装防水
- FRP防水
ここでは防水工事の種類と特徴を解説します。
シート防水
シート防水とは、防水シートを使用して建物の屋根や壁、床などに防水層を形成する防水工事の一つです。
材料には複数ありゴムシート防水や塩ビシートを使用する防水などがあります。
- ゴムシート防水:シート状に形成した合成ゴム糸の防水シートを接着剤や機械などで下地に貼り付け・固定して防水加工する防水工事法
- 塩ビシート防水:「塩化ビニル樹脂製」のシートを接着剤や機械などで下地に貼り付け・固定して防水加工を行う防水工事法
一般的なシート防水の仕組み
シート防水は、接着剤や溶剤で下地にシートを接着することで防水を行う仕組みです。
使用される素材は上で解説したとおり「ゴム」「塩ビ」で、近年では塩ビの防水シートが主流となりつつあります。
その他にもアスファルト防水と呼ばれる合成繊維不織布のシートに液状に溶かしたアスファルトをしみ込ませてコーティングしたシートを二層以上に仕上げる防水工事法もあります。
また、シート防水の工事工程は以下のとおりです。
- 基礎面の処理(下地の処理)
- 下塗り(プライマー)
- 接着剤の塗布
- シートの敷設
- 端末部の処理
- トップコート
シート防水を実施する前に必ず必要な工程が基礎面の処理です。
基礎面に使用される素材の多くはコンクリートやモルタルで、これらの表面には凹凸や隙間があるので、その状態で防水シートを接着してもしっかりと密着しない可能性があります。
そのため、基礎面(下地面)に対してプライマーと呼ばれる下地処理材を塗布して防水シートの密着性を高めることが大切なのです。
基礎面の処理と下塗りが完了したら、次は防水シートを敷設します。
下地とシートを接着剤や溶剤でしっかり接着します。
このとき、防水シート同士や基礎面がしっかりと接着するよう、接着部分の処理も必要です。
防水シートを適切に敷設し終わったら、トップコートで仕上げを行います。
防水シートはUV光、つまり太陽からの紫外線に弱い素材もあるので、日焼け対策として上からトップコートを塗布する場合があります。
ただ、防水シートの中にはトップコートを必要としない素材もあるので、トップコートを塗布するかは素材と業者次第と言えるでしょう。
しっかりとトップコートを塗布し、乾けばシート防水工事は完了です。
シート防水のメリットとデメリット
シート防水のメリットとデメリットは以下のとおりです。
- メリット①施工が比較的簡単
- メリット②工期が短め
- メリット③下地を選ばない
- メリット④耐候性が強い
- メリット⑤工事後のメンテナンスがしやすい
シート防水は他の防水工事と比べて施工が比較的簡単な防水工事とされています。
また、防水シートは比較的軽量なので施工がしやすいという利点もあります。
その他にもシート帽子の工期は最短3日〜1週間程度と短めです。加えてシートを上から接着するだけなので下地を選ばず施工できる点も魅力でしょう。
これ以外にも、自然環境の変化や、気候条件、紫外線などの影響に対して、耐えることができる耐候性があることや、工事後のメンテナンスもしやすいというメリットもあります。
一方、シート防水のデメリットは以下のとおりです。
- 施工費用が高め
- 施工には専門的な技術が必要
- 複雑な形状には不向き
シート防水は、施工費用が高めでシート交換などのメンテナンス費用も別途かかります。
そのため、初期投資やランニングコストがかかりやすい点がデメリットでしょう。
また、施工費用にもかかわるデメリットとして、防水シートは柔軟性があるので取り扱いが難しいことから専門的な知識や技術を持った業者が行う必要があります。
それに伴い、どうしてもトータルの施工費用が高めになる傾向があるのです。
また、リフォーム業者や塗装業者によってはシート防水の経験が浅い場合もあり、施工ミスによって防水性が発揮できなかったり、耐久性自体が低下する可能性もある点もデメリットです。
その他にも、下地を選ばず施工できる点はメリットでも凹凸がある場所など複雑な形状の箇所には施工しにくい点もデメリットとして挙げられます。
塗装防水
塗装防水とは、外壁の表面を塗料でコーティングして雨や湿気、紫外線などによって外壁が痛むのを防ぐ防水工事です。
塗装防水は、建物や構造物の屋根や壁、床など、さまざまな箇所で用いられます。
また塗装防水で使用される塗料には「アクリル」「ウレタン」「シリコン」「フッ素」などがあり、中でもウレタンを使用した防水工事を行う業者が多いです。
塗装防水の基本的な仕組み
塗料防水は、外壁の表面をコーティングして防水を行う仕組みです。
一般的にはアクリル系やウレタン系の防水効果が期待できる塗料が使用されています。
また塗料防水の工事工程は以下のとおりです。
- 検査・診断
- 下地処理
- 防水塗料の塗布
- 仕上げ
塗装防水を実施する前は、まず建物や構造物の状態を検査・診断する必要があります。
例えば塗装防水が可能な状態か、どのような材質が使用されているのかなどです。
先ほど解説したシート防水は、基本的に下地がどのような素材であっても問題がないケースも多いですが、塗装防水の場合は事前の検査と診断がとても重要です。
次に、塗装防水を実施する箇所に対して表面をクリーニングして汚れや錆を除去します。
また、現在塗布されている塗料に剥離が見られる場合は、この箇所も併せて除去します。
その他にも塗布する箇所に凹凸がある場合も同様です。
下地処理が完了したら、次は防水塗装を実施していきます。
塗料はスプレーやローラーなどを利用して行い、複数回に分けて丁寧に塗布していくのがコツです。
塗料を塗布した後は、一定期間乾燥させる時間も必要なので、時間を置いて乾燥が確認出来たら次のステップである仕上げに移ります。
防水塗料が完全に乾燥したら表面に仕上げ材と呼ばれるものを塗布します。
この仕上げ材は、塗料面をコーティングして耐久性を維持するだけでなく、塗料の色や質感を整えてくれる優れものです。
そして最後に防水性能を発揮しているかをチェックして問題がなければ工事完了となります。
塗装防水のメリットとデメリット
塗装防水のメリットは以下のとおりです。
- 施工費用が比較的安め
- 複雑な形状でも問題なく塗布できる
- 液状の液体を塗布して固めるので、継ぎ目ができず仕上がりが綺麗に見える
塗装防水はシート防水と比較して施工費用が安く済みます。例えば通常の防水工事だと産業廃棄物が出る工事法を採用する業者もありますが、塗装防水の場合は元々ある防水層の上から上塗りできるので、産業廃棄物を出さず、その分の費用も抑えられます。
とにかく費用を抑えてベランダに防水工事を行いたい方は塗装防水がおすすめです。
また防水性能が期待できる塗料を必要な箇所に塗装する工事なので、複雑な形状の場所でも問題なく塗布できる点もメリットと言えるでしょう。
その他にも、塗料を塗布する工事なので継ぎ目が出来ず外観も綺麗に仕上がることや、防水層の上から上塗りできるので、産業廃棄物を出さず、その分費用を抑えられます。
一方、塗装防水のデメリットは以下のとおりです。
- 均一な塗布ができるよう業者の高い技術力が必要
- 乾かすための時間がかかる
- 耐用年数が短め
塗布防水はどれだけ均一に塗料を塗布できるかがとても重要です。
ムラのある箇所は水分を含んで膨らんでしまう可能性があり、そうなるとせっかく塗装防水を実施していても思ったような効果が期待できなくなってしまうからです。
また、均一に塗布するためには塗装防水に対する技術力を持った業者の選定が必要になります。
その他にも、塗装防水は塗料が劣化すれば防水効果が減少してしまうので、それに伴い耐用年数も10年前後と短めである点もデメリットと言えるでしょう。
FRP防水
FRP防水とは「Fiberglass Reinforced Plastic」の略で日本語にするとガラス繊維強化プラスチック(GRP)とも呼ばれています。
「繊維強化プラスチック(Fiber reinforced Plastics)」のシートを防水加工したい部分に敷いて、その上から樹脂を塗布して硬化させる防水工事法です。
FRP防水の特徴と施工方法
FRPの防水の大きな特徴は強度と耐久性があるFRP素材を利用している点です。
防水工事の種類によっては重量がある素材を使用するものもありますが、FRP防水では軽量でありながら防水性や耐候性、耐水性が大いに期待できます。
またFRP防水の施工方法は以下のとおりです。
- 下地処理
- FRP防水シートの貼り付け
- レジンの塗布・固定
- 仕上げ
FRP防水を行う前は、他の防水工事と同様に建物や構造物の下地処理を行います。
古い防水層の撤去や洗浄、穴やひび割れの修復、塗布部分の平滑化が代表的です。
その後、FRP防水シートを下地に貼り付け、シートの間に隙間ができないよう慎重にシートを重ね合わせます。隙間があると機能的な性能が半減してしまうので業者の技術力も重要です。
FRP防水シートを貼り付け終わったら、次はガラス繊維と樹木を混ぜ合わせてペースト状にしたレジンをシートの上に塗布します。
ポイントとしては繊維の方向や強度に注意しつつ、綺麗に層を重ねて固定を行います。
これもまた業者の技術力が重要な作業と言えるでしょう。
FRP防水シートがしっかりと固定されたのを確認したら、最後にトップコートを塗布して完了です。
トップコートを塗布すると、FRP防水シートの保護に加えて美しい仕上がりになることができます。
FRP防水のメリットとデメリット
FRP防水のメリットは以下のとおりです。
- 耐久性が高い
- 軽量
- 防水性への高い実績がある
- 工期が短め
FRP防水は耐久性や摩耗性に対して非常に特化しています。
そのため、ベランダはもちろん人が歩く機会の多い箇所に適している防水工事です。
また耐久性と摩耗性に優れているFRP防水は、それ以外にも1㎡に対し重さは3〜5kgと軽量なので建物への負担軽減にも繋がります。築年数が経過している建物に優しい点もメリットです。
その他にも、FRP防水はバスタブやロケットなど防水性がとても重要なものに利用されることの多い実績がある防水工事法です。信頼性の高さも魅力と言えます。
FRP防水の工期は最短1日〜2日と今回解説している防水工事の中で最も短いです。
工期が短ければ費用面でも、建物に住む住民や利用者の負担も大幅に減少できます。
一方、FRP防水のデメリットは以下のとおりです。
- 費用が高め
- 硬化させるまでの間、独特なニオイがする
- 伸縮性は期待できない
FRP防水は非常に優れた素材を使用するので費用が高めになる傾向があります。
ベランダのような広い箇所に対してFRP防水工事を実施する場合、費用面が気になる場合も。
またFRP防水で使用される素材は硬化するまでの間、ポリエステル樹脂特有の刺激臭がします。
何度もニオイを嗅いでいる業者などはあまり気にならない方もいるようですが、初めてこのニオイを嗅いだ方の中には「鼻がまがりそう」「本当にくさい」と答える方も大勢いる程です。
FRP防水の硬化時間は季節によって異なり、暑い夏だと3時間、冬の場合は一晩かかる場合も。
完全に硬化してしまえばにおわなくなりますが、それまでの期間を苦痛に感じる可能性もあります。
この他にも、耐久性や摩耗性、軽量と優れた面が多いFRP防水ですが、伸縮性は期待できません。
伸縮する可能性がある木造住宅には向いておらず、使用する現場を選ぶこともデメリットです。
適切な防水工事の選び方
次は、ベランダに防水工事を依頼したい方に向けて、適切な防水工事の選び方を3つ解説します。
- ベランダの構造や用途に合わせた選択
- 予算や耐久性のバランスを考慮
- 専門家の意見を参考にする
ベランダの構造や用途に合わせた選択
ベランダの構造には以下3つの種類があります。
- フレーム構造
- ポーチ構造
- ハンガー構造
フレーム構造は木造住宅に多い構造で、柱や梁(はり)などの骨組みを作った上に床を設置します。
2つ目のポーチ構造は、建物の外壁と一体化した構造で、鉄筋コンクリートや鉄骨が多く、3つ目のハンガー構造は建物の外側から伸びる支持棒に床を取り付ける構造です。
それぞれの種類によって、適切な防水工事は異なります。
またベランダの用途には以下のようなものが該当します。
- 物干し場
- ガーデニング
- リラックススペース
- ペットの遊び場
ベランダと言えば、基本的に洗濯物を干す場所として利用されることが多いです。
複数ある用途の中で最も多いのではないでしょうか。
その他にも、鉢植えやプランターを設置して大好きなガーデニングを楽しむ際や、椅子やテーブルを置いてリラックススペースに使用する方もいるかと思います。
お家にペットがいる場合は遊び場として活用したい方もいるかもしれませんね。
ベランダには人それぞれ用途があるので、この用途に合った防水工事方を選ぶことが大切です。
予算や耐久性のバランスを考慮
防水工事には種類ごとに予算や耐久性などが異なります。
そのため、ご自身がどの程度の予算内で防水工事を依頼したいのかという点や、上で紹介したベランダの用途によって必要な耐久性も考慮して適切な防水工事を選ぶ必要があります。
できるだけ安く防水工事を依頼したい場合は「塗装防水」、耐久性や防水性の実績で選ぶなら「FRP防水」など、どの防水工事が良いか迷った方は専門家へ相談してみてください。
専門家の意見を参考にする
「いまいちどの防水工事が適しているかわからない」という方は外壁塗装業者や大規模修繕を得意とする業者などの専門家への相談が最も信頼できるでしょう。
一度ベランダを直接見てもらい、適切な防水工事方法や、工事に関するメリットデメリット、そしておおよその費用を算出してもらうこともできます。
インターネット上では無料で相談できる窓口や見積もりサイトも多く存在していますので、それらの口コミをチェックしつつ信頼できる業者を選ぶことにも繋がります。
防水工事の注意点とポイント
次は、防水工事の注意点とポイントを3つ解説しますので、ぜひ参考にしてください。
- 適切な施工時期と条件
- 隅角部や配管周りの性交の重要性
- 定期的なメンテナンスの実施
適切な施工時期と条件
防水工事には適切な施工時期と条件があります。
- 気温が高く湿度が低い時期
- 雨の少ない時期
気温が高く湿度が低い時期は、安定した気候が続くことが多いので予期せぬ雨や風などによる作業の中断で工期を延長するなどのトラブルが起こりにくいです。
またこの時期は塗料の乾燥時間も早く、工期を短縮できるというメリットもあります。
その他にも、雨がよく降る梅雨の時期は、雨によって塗料が濡れたり、工事に使用する素材が濡れたりするリスクがあるので、せっかく工事を実施しても防水効果を損ねる可能性があります。
これらの内容を含め、雨の少ない時期も防水工事に適切な施行時期と条件と言えるでしょう。
隅角部や配管周りの施工の重要性
隅角部(ぐうかくぶ)とは、壁面が折れ曲がっている部分のことを指します。
この隅角部と配管周りの施工は防水工事において非常に重要なポイントです。
隅角部や配管周りは雨や湿気などによって水がたまりやすい箇所で、雨漏りや水漏れの原因となる可能性があります。そのため、この2つは防水工事を行う際、忘れずに防水処理を行いましょう。
防水工事内容としては、コーキング剤と呼ばれる外壁同士を繋ぐ際や、外壁塗装時によく使用される素材を使用して水が入り込まないように密封します。
また、コーキング剤は経年劣化によって割れたり、縮んだりする可能性があるので一度コーキング剤を使用して防水工事を行ったら、定期的な点検・メンテナンスを行いましょう。
定期的なメンテナンスの実施
これは防水工事だけではありませんが、工事完了後も定期的なメンテナンスの実施を忘れずに。
一般的に、防水のメンテナンスは10年〜15年に1回周期で行うことが多いです。
構造などによって多少前後する可能性はありますが、目安として覚えておきましょう。
また、防水メンテナンスが必要とされるサインは以下のようなものが挙げられます。
- 色褪せ
- ひび割れ
- 剥がれ
- 膨れ
- チョーキング「白亜化現象」など
チョーキング(白亜化現象)とは、工事を施工した部分を触った際、指に白い粉がつくことを指しており、このサインがあらわれた場合にはなるべく早くメンテナンスが必要です。
そのまま放っておくと後々メンテナンスや修繕を行う際、予想以上に劣化・老朽化が進んでいることで高額な費用を請求される可能性があります。
定期的なメンテナンスは予期せぬトラブルによる支出を抑え、長期的なスパンで見ればコスト削減に役立ってくれるでしょう。
防水工事の費用と相場
ここでは防水工事の費用と相場を解説します。
費用や相場は使用する建築材料や塗料、そして工事範囲によって異なりますのでご自宅や管理している建物の場合はいくらくらいになるのか、専門家に相談してみてください。
工事の種類ごとの費用相場
それでは、本記事で紹介した工事の種類ごとに費用相場を見ていきましょう。
シート防水の費用相場は、使用する建築材料によって異なります。
| 工法 | 単価 |
| ウレタン防水 | 約7,500円/㎡ |
| シート防水 | 約8,000円/㎡ |
| FPR防水 | 約9,000円/㎡ |
| アスファルト防水 | 約8,000円/㎡ |
| 塩ビシート防水 | 約4,000円〜7,000円/㎡ |
| ゴム防水 | 約4,000円〜7,000円/㎡ |
防水工事で最も安いのはシート防水で、塩ビ・ゴムともに1㎡あたり約4,000円〜7,000円です。
一方最も高いのはFRP防水となっています。信頼性と実績で考えるとこの高さもうなずけます。
またこれは一つの参考であり、防水工事を依頼したいベランダのサイズや用途などによって異なる可能性がありますので、まずは一度専門家に調査を依頼して明確な料金を算出してもらいましょう。
費用を抑えるためのポイント
ベランダの防水工事費用を抑えるためのポイントは以下のとおりです。
- 複数の業者から見積もりを取る
- 材料選び
- 定期的なメンテナンス
- 早い段階での施工
ベランダの防水工事だけには限りませんが、工事費用をなるべく抑えたい場合は複数の業者から見積もりを取って適正な価格で依頼できるようにすることが大切になります。
複数の業者から見積もりを取る際は一括見積もりを利用すると円滑に見積もりを取ることができますので、ぜひ利用してみてください。
※注意点として、業者の中には安い見積もりでお客さんを「釣って」集客率しよう考えている業者もいます。あまりにも安い場合は以下の「優良業者を選定するポイント」を参考にしてください。
- インターネット上での口コミや評判はどうか
- ベランダを含む建物の防水工事に関する実績はあるか
- 実際に会って話した際の対応はどうか・人柄もチェック
- なぜ他の業者よりも安いのかを質問して回答に納得できるか
- 施工後の保証やアフターサポートはあるか
- 施工を担当する業者の知識は豊富か・高い技術力を持っているか
これらのポイントは、優良業者に共通した特徴となります。
もちろんすべてをクリアしている業者でなければならないわけではありませんが、ポイントを意識して選ぶと納得の行く価格でハイレベルな仕上がりが期待できるでしょう。
次に、先ほど料金相場で解説したとおり、防水工事に使用する建築材料の費用は異なります。
そのため、なるべく安く費用を抑えたいならばシート防水での防水工事がおすすめです。
ただし、実際に防水工事を依頼するベランダを専門家や業者が調査した際に「この素材が適している」と適した建築材料や塗料を指定される場合もあります。
このような場合、しっかりと専門家や業者と話し合い、どうしても納得が行かない場合は別の業者へ話を聞いてみても良いでしょう。
次に、定期的なメンテナンスはもしものトラブルを回避するために有効です。
防水工事は1回の工事で半永久的に建物の健康が維持できるわけではないので、定期的にメンテナンスを行って早い段階で施工を依頼することで無駄な支出を抑える効果が期待できます。
補助金や助成金の活用方法
ここまでに解説した防水工事の費用を抑えるためのポイントに加えて、何らかの工事を行う際は補助金や助成金が国・地方自治体から受け取れる場合もあります。
一例として埼玉県富士見市では、屋根の防水工事や雨どいの修理を含むリフォーム全般に対して工事費の5%を補助する制度を利用した場合、最大10万円お得に防水工事が行えます。
一般的に防水工事は大規模修繕工事などの大がかりな工事に比べると補助・助成してもらえる金額は10万円〜20万円が相場です。
また、防水工事で補助・助成してもらえる精度をどの地域で利用できるのかは以下の「地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」などを利用してみましょう。
「地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」
では実際に「この補助・助成を受けたい」と考えた場合について。
多くの制度では申請・支給条件を設けています。
申請・支給条件として設けられているものの一例は以下のとおりです。
- 補助金や助成金を申請する地域に住んでいること
- 過去に同じような内容の補助金や助成金を受け取っていないこと
- 県民税や市民税の滞納はしていないこと
- 商業目的ではなく、居住を目的としていること
- 制度の目的に当てはまる工事内容であること
これは一例ですが、このような申請・支給条件を設けている場合が多いので予め問い合わせておくと円滑に申請まで進められます。
そして申請する際はしっかりと申請期限に間に合うよう準備を整えることや、補助・助成制度の条件に当てはまっているかもチェックしてください。
また実際に申請する際、必ず必要となる書類は以下の3つとなります。
補助・助成制度によって異なる場合もありますので、参考程度にご覧ください。
- ベランダ工事を行う建物の見取り図や平面図
- 見積書の写し
- 税金を納めている証明ができるもの
初めての申請は期限遅れや必要書類の不足などでバタバタしやすいです。
こちらに記載した情報をもとに余裕を持って申請できるよう準備しておきましょう。
まとめ
本記事では、ベランダの防水工事に関して、重要性や工事の種類・特徴を解説しました。
また一例ではありますが、費用相場や補助金や助成金の活用・申請条件についてもあわせて紹介しましたので、ぜひ今後防水工事を業者へ依頼する際にご活用ください。
ベランダの防水工事と一言にしても、工事内容やチェックするポイントは複数あります。
特に業者選びは工事の成功を左右するといっても過言ではありませんので入念に選びましょう。
大規模修繕は新東亜工業がおすすめ!

中間マージン0だから他社より安い費用で工事が可能
※中間マージン=仲介手数料
- 大規模修繕工事
- 解体工事
- 防水工事
- 外壁塗装
- 屋根工事
- シーリング工事
- 長尺シート工事
- 下地補修工事
- 足場工事
- タイル工事
- 洗浄工事
- 電気、水道、外溝工事等
大きな強みは「自社で完結」
施工価格と見積りには絶対的な自信を持っていますので、他社との相見積りも大歓迎です。
ご予算と現場調査の結果、長期的な視点での資産価値向上をバランスよく考慮し、お客様にとってベストな選択肢をご提案します。